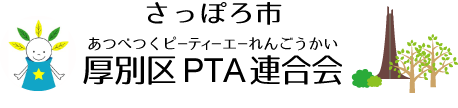10月5日(日)
第72回日本PTA北海道ブロック研究大会 宗谷管内・稚内大会全体会が行われました

大会スローガン
「てっぺんから広げよう!子育ての輪と和と話」
大会主題
未来を担う子どもたちの今とこれからの幸せ(well being)を願い、学び合い、連携し合うPTAをめざして
全体会、記念講演は
元THE BOOMボーカルの宮沢和史さん
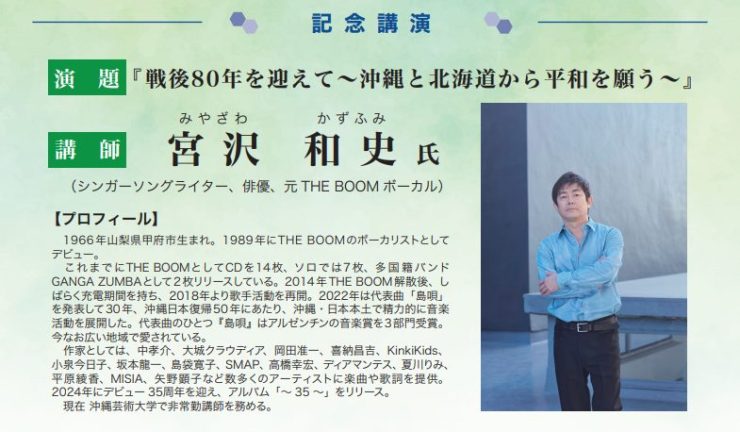
「旅での出会いが次の曲に反映される」
沖縄民謡が好きで、より深く知りたくて20代の頃沖縄へ
沖縄を知って世界は広いと感じ、音楽人生が変わったと話します
後に誕生する名曲「島唄」が作られるきっかけとなった沖縄との出会い
また曲に込められた想いを伝えて頂きました
訪れた沖縄は、1945年の沖縄戦争の傷跡が残っていて
「戦争はこんなに身近だった」と気付きます
戦争についてより深く知るためひめゆり平和祈念資料館へ
資料館の歴史はまだ浅く設立されたのは1989年、戦争当時を知るひめゆり学徒隊の方がお話を聞かせてくれます
終戦から資料館設立までに時間を要した理由を学徒隊の方はこう話したそうです
「生き残ってしまった罪悪感」
軍民あわせて20万人もの尊い生命が奪われた戦争
攻撃により亡くなるだけではなく、集団自決で命を落とす人も沢山居た
爆弾にやられた、銃で撃たれて死んでしまった無念、それよりも悲しい自決と悲劇
宮沢さんは沢山の言葉に衝撃を受けます
生き残ってしまった
だけど「私達が伝えなくては!」
同級生の無念を晴らすために、と語り続けてきた
そう話してくれた学徒隊の方に感謝
この想いを歌にしてお返ししたい!と出来た曲が「島唄」です
島唄の歌詞には、宮沢さんの沢山の想いが詰まっています
※著作権の関係上、歌詞の全文を載せる事はできませんが、是非歌詞を検索してみてください
デイゴの花が…
「デイゴ」春に咲く花
沖縄ではデイゴが咲き乱れると強い台風が来ると言い伝えがあり
戦争のあった年には春にデイゴが沢山咲いてしまい、戦争攻撃という嵐が来てしまった
繰り返す悲しみ…
帝国主義が何度も起こる沖縄を現した言葉
ウージの森で…
「ウージ」さとうきび
数メートルまで成長するため森のように感じる
さとうきび畑で仲良く遊んだ友達が、なぜ死んでしまって別れなくてはならなくなったんだろう
さとうきび畑で恋をした2人が、さとうきび畑の下でなぜ自決しなくてはならなかったんだろう
沖縄民謡にも使われる琉球音階にはレとラが無く、島唄も琉球音階を使っていますが、ウージの森で…この部分には琉球音階は使われておらず、三線も演奏されていません
「戦争で沖縄の人が選ばざるを得なかった死。沖縄の音階は使えない」
また無念や悲しみを表現するのに、三線を演奏する事が出来なかったとのこと
音楽的手法にも、宮沢さんのメッセージが込められています
この歌が沢山の人に届いて、想いが伝わって
争いの無い平和な世の中が来たら、この歌は歌う必要が無い
いつか、この歌を歌わなくてもいい日が来てほしい
講演の最後には宮沢さんが「島唄」を歌って下さいました
沢山の想いを知ってから聞いた歌声に、会場では涙を流す人も…
大きな拍手に包まれて、全体会は終了となりました
くるちの杜100年プロジェクト
島唄の演奏の際にも使われている「三線」
沖縄文化を象徴する文化の一つとして知られる三線ですが、今は作る材料が全て輸入です
宮沢さんが三線職人さんと食事に行った時に、こんなことを言われました
「島唄が売れてから三線をやってみたいという人が増えて、国産で三線が作れなくなったんだよ」
職人さんは冗談のように話していたが、宮沢さんは笑えなかったと言います
プロの三線奏者や本当に使いたい人の手に三線が届かなくなってしまったのでは?
良い事をしたなんて思っていたけど、とんでもない事をしてしまったのかもしれない…
何かできる事はないだろうか?
そんな想いから始動したのが「くるちの杜100年プロジェクト」
三線に使われている琉球黒檀の「くるち」を育てるプロジェクト
くるちは成長して立派に育つまでに100年かかるとされています
宮沢さんは、自分は生きていなくても、この木が大きくなり、三線となり、その音色が沖縄中に響いて欲しいとの願いを込めて活動しています
「もし100年後、立派に育っていたとしたら、その間争いが無く平和だったということ」とも話されていました
全体会に参加した伊藤副会長は
自分が良かれと思ってやっていたことは相手にとっては負担感を与えてしまってるかもしれない。ということの気づきと、そこからじゃあどうしたら相手に喜びを与えられるのかという行動がその先のプロジェクトに繋がるということがPTA活動にも通じるなと感じました
と話していました
それぞれが沢山の学びや気付きのある大会参加となりました